資格予備校の講義を受講したときに限らず、独学の方にも同じことが言えると思うのですが、テキストを入手して初めて読むときはじっくり読む必要はないと考えています。
初めてテキストを読んだとき、一文字たりとも漏らすことなく集中して読むことを心がけました。そして司法書士試験のテキストは分厚いです。標準的なものでも合計5000ページはあるのではないでしょうか。これを時間をかけて読むと全科目1周するのに2カ月はかかります。このペースではとても何周も回せません。
初回のテキストの読み方
私はテキストを集中して、民法→不動産登記法→会社法・商業登記法→憲法→刑法→民事訴訟法→民事執行法→民事保全法→供託法→司法書士法の順で読み、2周目の民法に戻った時、とあることに気付きました。それは「民法のことを何も覚えていない」ということです。一部の特殊能力を持っている方でしたら記憶している可能性もありますが、いくら集中していたとしても、2カ月前に読んだことなど忘れるはずですので、それを予め織り込んだ上で、初回は流し読みで構わないと思います。どうせ忘れるものを集中して覚えようとするのは時間がもったいないです。
初回のテキスト読みが終わったらどうする?
過去問に突入します。おそらくこの時点で問題は解けませんが、それで構いません。問題を読み、問われている内容を理解した上ですぐに解答と解説を見ます。そのようにして、過去問集をどんどん進めます。解説を読んでわからないことがあればテキストの該当箇所を読み、その論点で問われている内容を理解することに集中しましょう。この段階でテキストは「辞書化」します。つまり何度も素読する必要を無くし、アウトプットをしている中で理解を深めたい時だけ戻ってくるツールになります。テキスト素読は集中力を失っていても読み進めることができてしまうため、学習効果を感じにくいです。
なお、過去問メインではなく、テキストメインで学習を進めたい場合についても、暗記ペンなどでキーワード(重要な単語等)にマーキングをし、暗記ペンに付属しているシートを当てながらテキスト読みをするのも効果的です。これなら単純な素読にはならず、頭を働かせながら読むことができるからです。これを毎回することで、そのキーワードに対して紐づいた知識が反射的に頭から取り出せるようになります。
結局必要なのは
メインに据える教材をテキスト、過去問いずれにする場合でも、思考の余地を挟む仕組み化をしておくことが最善と考えます。特にテキスト読み(インプット型)の場合は文字を目で追うだけになりがちなので、前述した暗記ペンなどで一工夫をいれると学習効率が飛躍的に上がると思います。

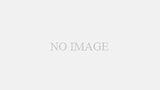
コメント