10年程前になりますが、行政書士試験を受験しました。当時はまだ司法書士試験に合格しておらず、ようやく午前の部で基準点に到達するくらいの成績でした。どうしても試験本番に弱いという自覚があり、それは当然ですが答練や模試といったものでは訓練できませんでした。
そこで、再度行政書士の勉強を開始し、行政書士試験本試験で本番の練習をしようと考えました。いずれ行政書士資格は取ろうと思ってましたので、ここがその機会だと考えました。
そう考えたのが、その年の司法書士試験が終わり、基準点発表がされその年の司法書士試験の不合格が確定した数日後でしたので、8月中旬でした。行政書士試験は11月ですので急いで試験対策をしなければなりません。伊藤塾に「司法書士試験受験生のための行政書士試験スピード講座」なるものがありましたので、早速受講しました。
行政書士の試験科目は一般知識・基礎法学・憲法・民法・会社法・行政法で、このうち司法書士受験生は憲法・民法・会社法は試験科目が被ります。そのため、講座では主に一般知識と行政法の講義のみでに留まります。一般知識科目の、政治・経済・社会に関しては対策がほぼできません。というのは、範囲が広すぎ、テキストに書いていることも役に立たないので、この分野に関しては一問も正解できませんでした。法律職の試験においてあまり意味をなさない出題の気がします。
一般知識のうち政治・経済・社会については捨て、他はすべて拾えるようにしました。でないと足切りになるからです。次に行政法。行政法という名の法律があるわけではなく、行政手続法、行政不服審査法、行政事件訴訟法、国家賠償法及び地方自治法という個別の法律をひとまとめにして行政法と呼びます。ここから試験全体の半分くらいの出題があるので、ここは必死に勉強しました。行政書士試験には記述式が3問出題され、そのうち1問は行政法からの出題です。司法書士試験受験生であれば残り2問の民法で得点を稼げますので、私はここは得点計画から外しました。実際サッパリわかりませんでした。
ただ、試験まで時間がそれほどないため、講義を1周しわからない部分があっても問題演習に入りました。問題演習に使ったのは一問一答タイプの問題集を買ってきて、ひたすらそれを回しました。
合格革命 行政書士 一問一答式 出るとこ千問ノック 2025年度 [基本テキストの重要ポイントを1000問のオリジナル問題で総チェック](早稲田経営出版)
何度も回し、覚えた肢はどんどん削り回転数を増やしました。この方法で行政法は8割を得点することができましたので、十分だったと思います。

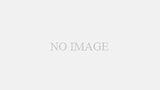
コメント