初学者が講義動画を見るときの方法について、自身の失敗談を交えてお話します。
失敗談
某資格予備校の講座を受けた際、大量の講義DVD(数えたら120枚ちょっとありました)を消化することが目的となっていました。講師が言う「ここをカッコで括っておいてください」「ここにアンダーラインを引いておいてください」に対して、言われるがままにその通りにしておりました。そしてそのうち、それがDVDを見る目的が、勉強ではなく「作業」になりました。
当然ながら成長を実感できませんでしたが、当時はそれが正しいと信じて全てのDVDを見ました。そして、ここからが失敗で、テキストのアンダーラインを引いている箇所をノートに書き写すという作業を始めてしまいました。ここまでの時点で、自分の頭で考えるという工程を経ていません。一番重要なアンダーラインを引いたりしてカスタムしたテキストを使った「復習」という部分をすっ飛ばして「勉強してる感じ」のことだけをやっていたので、せっかくの可処分時間の使い方としては非効率だったと思います。
ただ、このような経験をしましたが「全く意味がなかった」ではなく、非効率な方法を一つ体験できたと考えると前向きに考えることで次の方策を練ることができましたので、血肉にはなっているのかなと思います。
この経験からの対策
講義のDVDやストリーミングを視聴しているとどうしても飽きます。そして集中力を失います。でもカリキュラムを消化しなければと思います。私はそうでした。その場合、どうしようもないと諦めますが、気になれば動画を再度みればいいだけです。ただし私は同じ講義を2度見ることはなかったと記憶しています。
資格予備校の講義を受けるとテキストが届けられます。講義内容としては重要論点のランク付け、重要論点の解説、重要箇所のマーカー部分の指示が多いはずです。少なくとも私が受講した講義においてはそのパターンが全てでした。暗記すべき項目を語呂合わせで提供してくれる講師もいます。
テキストは図解などで分かり易く解説してありますので、復習の際に少し考えこむことがあっても理解はできると思います。そこで重要なのは理解しようと考えることです。紙に図解を描き起こしても構いません。むしろそうすることで記憶に定着しやすくなりますし、試験の際に、頭の中に何度も描いた図解が再現されるようになります。結局、講義は集中して聞けるに越したことはありませんが、最低限アンダーラインは漏らさずに引けるくらいのレベルで講義を視聴できていればよいと思います。
私はノートを作成し、テキストの重要箇所の写経のようなことをしていましたが、これは大変効率が悪いと感じたため止めました。これを止めるまでに結構な時間がかかりましたが。自分自身を「書いて覚えるタイプ」だと勝手に評価していたのですが、結果あまり覚えられませんでした(笑)
大事なのはアンダーラインが引かれたテキストを使って、どのように復習するかです。上に書いたように「作業(講義聞きながらアンダーライン引き)」に「作業(ノート写経)」を重ねてはいけません。「作業」の後に「思考(テキストや過去問を使ってアウトプットしてみる)」を重ねることが必要になります。
また時間節約のため、写経やメモ用ノートは別途作成せず、テキストに直接書き込んでいくべきだと思います。そうすることで、教材の出し入れをイチイチする手間が省けますし、「きれいなノートを作ろう」という手段の目的化の種を一つ潰すことができます。本に書き込みを入れることに躊躇いを感じる方もいるかもしれませんが、どんどんカスタムしていきましょう。

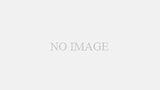
コメント